|
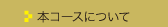
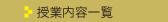
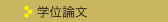
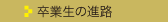
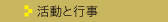
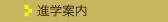 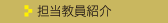
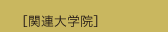 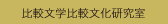 
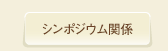
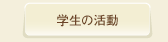
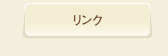
Copyright 2006 © All rights reserved by
The University of Tokyo
|
伊藤 徳也 いとうのりや
| 専門 |
| 比較文化論(近現代中国文学・美学、審美主義・デカダンス論、現代日中文化関係論 |
| |
| シニアで主に担当する予定の授業科目名 |
| 比較文学論、テクスト精読法、共通外国語(中国語) |
| |
| 旧シニアで主に行っていた授業内容名 |
| 比較文学論、現代文化構造論基礎 |
| |
| この新しいコースと学生さんたちに期待すること |
| 「文学」はLiteratureであると同時に「文」「学」だ。「芸術」はartであると同時に「芸」「術」だ。この二つの日本語は、西洋の近代世界だけではなく、東アジア共通の古典世界ともつながっている。これらは単純な翻訳語ではない。そうした二つのことばの意味の多層性を私は大切にしている。それが私にとっての「比較」の意味だ。究極的に問われるべきなのは、「文学」を含む広義の「芸術」の現実的な意義だと私は考えている。現代社会を生きる私たちにとっての、日常生活におけるアクチュアルな意義だ。「芸術」なんてどうでもいい。それもひとつの態度だ。でも、その時の「芸術」とは何だろうか。それは大方「生活」と切り離され、対象として自立(孤立)した「芸術」だろう。それに対して「生活」を「芸術」と見なそうとする態度がある。周作人はそのような態度から「生活の芸術」論を語った。その時「芸術」は、「生活」から切り離された対象物ではなく、人間が生きることそれ自体になる。「芸術のための芸術」と「生活のための生活」と「科学のための科学」三つのモダニティのデカダンスを、現代社会の日常を生きる「凡人」として達人的に充実させる「中庸」の技法。それがそのまま「芸術」になる。ただ彼は「芸術」の中でも、文章を書くことには特権的な地位を与えていた。私もそのようなものを広義の「文学」として重視している。そして、日本文化に対して繊細で親身な理解を寄せた周作人は、日本文化の中にも「生活の芸術」の重要な要素を見出していた。以上のようなことは、「生活の芸術化」とか「日常生活の審美化」といったテーマと結びついて、近年の東アジア(特に日本と中国語圏)における文化の交流・交渉・衝突という研究課題へと私を導いている。 |
|