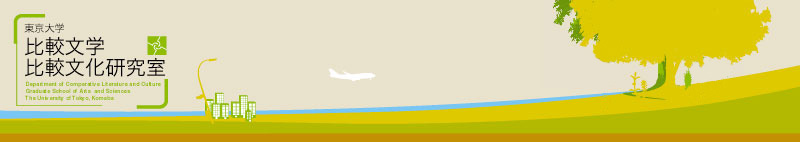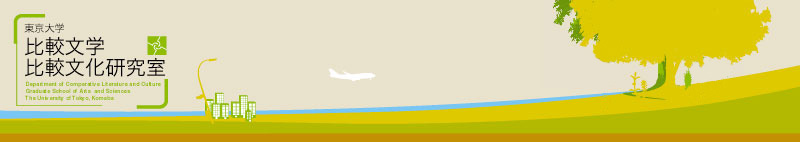ディスカッサントとして参加した大学院生による、講義についての感想です。
4月15日・三谷博先生「三代(孝明・明治・大正)の即位儀礼」について
今回は、孝明・明治・大正三代の間の即位儀礼に見られた変化について、写真や図を多数用いながらの講義がなされました。孝明天皇の例では、天皇の禮服である袞冕(こんべん)十二章や王冠をはじめ、儀礼が高度に中国風であることに驚いた人も少なくなかったのではないでしょうか。明治天皇の時代になると、儀礼の「純日本化」が推進されたほか、参列者層の拡大によって、万機を公論に決する、新しい政治を具現化する試みがなされます。さらに大正天皇の時代には、西洋の価値観が反映され、夫婦ペアや外国人の参列、また、参列者の洋装が始まります。
単に儀礼の次第や三代における変更点を紹介するだけでなく、変化から維新の意味を読み解く視点に、歴史分析のおもしろさを感じた人もいることでしょう。間もなく駒場の美術博物館で開催される「王朝貴族の装束展」には、大正天皇の即位儀礼に用いられた装束が展示されます。ぜひこれらの装束を実際にご覧になって、受講生の皆さんにも、歴史的な意味を考察してもらえればと思っています。
永井久美子(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
4月22日・折茂克哉先生「モノで語る歴史 ─考古学と博物館」について
考古学者であり、教養学部美術博物館の展示を担当されてもいる折茂克哉先生のご講義は、さまざまな国で異なる時代に作られた復元図やジオラマ、またご専門のロシアの旧石器時代のお話などの具体例を多く用いながら、歴史を語るということの本質を正面から伝えてくださるものでした。同じテーマを扱いながらも、作られる復元図・復元像が作成者の立場や思想によりそれぞれ大きく異なるということを実例をもって目撃することは、歴史を語る際に無意識の偏見が必ず入り込むということをはっきりと認識できる貴重な経験となりました。
また、先生がおっしゃった、歴史を語るには歴史観をきちんと持つことが大切である、ということや、証拠だけでも想像力だけでも歴史は語れない、という言葉に感銘を受けた学生も多かったようです。展示製作者が無意識に持っている偏見が、展示等を通して観覧者に「常識」として伝えられ、無意識の偏見が再生産される、という指摘に接して、歴史学者、考古学者、学芸員等の仕事が社会に与える責任や、観覧者が批判的に展示等を見ることの大切さも改めて認識させられました。
中井真木(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
5月6日・平川南先生「古代国家と稲 ─1200年前の稲の品種札の発見から」について
国立歴史民俗博物館の平川南教授によるご講演は、古代の木簡(文字・記号を墨書した木片)のなかに、稲の品種名を記したものが見出されたことを紹介し、その発見が古代日本における地方支配の実態の解明に示唆を与えたことを説明するものでした。
平安期の木簡から、「畔越」や「古僧子」など、江戸時代の農書に挙げられている品種名と同じ名が二十種近くも確認できること自体が驚きですが、品種名を記録した付札が、地域支配の中心的役割を担っていた郡司の根拠地付近で多く出土していることから、稲作は支配層によって完全に管理・統制されていたものだという実態が見て取れます。その統制のもとで稲は貨幣としての価値を保ち、また、稲を強制的に民衆に貸し付ける制度(出挙)によって、古代の農民は律令国家の支配体系のなかに組み込まれていきました。古代における米の位置づけは、一貫して政治の道具であったと納得されます。
行政の現実をうつしだしている木簡などの出土文字史料を中心に用いることで、以上のスリリングな議論がなされたという点に、学生のみなさんは目を向けてもらいたいと思います。
福田武史(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
5月13日・井坂里穂先生「インド西部のパールシー(ゾロアスター教徒)と歴史記述」について
今回の講演は、一般的になじみの薄いゾロアスター教の、しかもインドでのコミュニティーがメインのテーマでした。元来イランに興ったゾロアスター教は、7世紀以降のイスラームの侵攻によって東方への移住を開始し、主にインドのボンベイ(現ムンバイ)に巨大なコミュニティーを構成したという事が、ゾロアスター教の基本的な知識を交えながら、解りやすく説明されました。更には、ゾロアスター教徒達の教育水準の高さと、他文化に対する柔軟さによって生存してきた歴史が語られました。
ゾロアスター教と言うと、何やら怪しげな儀式を行う古代の宗教である、という漠然としたイメージや、「拝火教」というキーワードによってのみ理解されている節がありますが、今回の講演で、実際のゾロアスター教の姿がお分かりになったと思います。教育によって自らを守り、常に時の支配者に従うことによって平安を勝ち取ってきた彼らの姿は、少し計算高く見える一方、少数派の生きる方法としての一つの理想を示しているようにも思えました。
小村優太(大学院・比較文学比較文化コース 修士課程)
5月20日・義江彰夫先生「日常生活からみた歴史の再構成 ―国風文化を中心に」について
本講義は、駒場博物館にて開催中の「王朝貴族の装束展―衣服を通してみる文化の国風化―」と連動するものでした。特に平安時代の貴族の日常生活(衣食住)に視点をすえ、社会内的問題と国際環境との関連を考慮しつつ、従来の社会史・社会文化史(風俗史・民俗学)を乗り越える新たな歴史像を構築しようとする一つの試みで、博物館にて実際に展示品を目にしながら講義を進めるという画期的な側面を持ったと言えます。以下は、講義時に発言した補足と疑問点です。
補足。本講義に多用された用語「国風化」が与えるイメージについて、一点注意を喚起したいと思います。それは、例えば『源氏物語』などの物語類からもうかがいうる、天皇―貴族のみやびな日常生活(衣食住)を支えたのは、物質面で見ればやはり唐物であった点です。具体的には装束の材料・着物にたきこめるお香の原料・お茶碗などの陶磁器その他になります。つまり「国風化」とは、現実の同時代的東アジア世界における〈日本化〉なのではなく、かつて借り物として導入した律令国家的外来文化(制度)との決別だったとするべきでしょう。
疑問点。柔装束の解説において、義江先生は、貴族の装束の変化には、実力を蓄えつつある地方豪族たちの服装など生活文化・習慣を意図的に吸収した(全く異なる服制を生み出すのではない)、彼らと基盤を共有する側面がうかがえる点を指摘されました。その共通基盤こそが、地方豪族支配に有効だったわけです。本講義の核となる興味深い論点だと思います。
以上の点に関する疑問:一方で、天皇―貴族たちは、展示品(大正期)にもうけつがれる絶対的にきらびやかな装束を身にまとうことで、地方豪族はじめ一般の人々との隔絶を、常に、見える形で示し続けなければならなくなったとも言えるのではないでしょうか(ただし天皇は公衆から見えない存在となりますが)。それは、借り物と言いうる律令制(や儒教/礼)的な自明の上下秩序・君臣関係が、「国風化」の過程で薄れていくにつれ必然的にそうならざるをえなくなったのではないでしょうか。新たな可視的な上下秩序を生み出すことと装束の変化とは連関するでしょうが、私の意見としては、例えば同時期に確立してくる〈穢れ〉観とも関係するのではないかと思います。先生は講義冒頭で、日常生活と人間の心の営みとの有機的連関を探るとの目論見を述べられましたが、可視的な身分秩序形成とリンクするような形での天皇―貴族の精神的営みの面にも興味がわいてきました。
手島崇裕(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
6月3日・米谷匡史先生「近代日本と東アジア ─さまざまな時/空間、さまざまな脱植民地化」について
米谷先生の講義では、「植民地問題」などの「歴史問題」を考える際の「歴史認識」のあり方が中心的なテーマとなりました。
講義ではまず、近況メディアを賑わす「靖国問題」や「戦後賠償問題」などの現代的な外交問題を切り口とし、「歴史問題」を正確に捉える為には、一国史観に偏った固定的な歴史認識の枠組に捕われず、「歴史問題」をより通時的かつ相互的な性格を持つ問題として常に再吟味・検討する、批判的な思考と視点を持つ事の重要性が唱えられました。
授業の前半部では、日本の植民地政策に関わる主要な条約や史実の意義を沖縄・朝鮮半島そして台湾などの「脱植民地化」した地域の立場から再吟味し、いかに日本の植民地政策が東アジア内の地域に、「国民国家」の枠に収まりきらない重層的な時/空間を生み出したかが説明されました。
後半部では、実際に植民地政策を直間に経験した個人の内面へと焦点が絞られ、在日朝鮮人詩人である金時鐘や沖縄人記者の新川明などの著作を資料に使い、制度的・政策的には消失しても、現代においても尚個人のアイデンティティーや意識に影を落とす「植民地問題」の禍根の深さについて語られました。
それまで「日本史」や「世界史」など、きれいにまとまった「歴史認識」を追随することに慣れていた学部生たちにとって、そのような「歴史認識」自体の再考を促す講義は、きっと多く啓示を含むものであったと思います。
小野瀬宗一郎(大学院・比較文学比較文化コース 修士課程)
6月10日・三浦篤先生「美術史学と歴史記述の変貌 ─エドゥアール・マネを中心に」について
一枚の絵からどのようなことが語りうるのか、美術史学の実証的方法論を中心に分析していただきました。取りあげた作品は、一九世紀フランスの画家エドゥアール・マネが1863年に制作し、1865年のサロン(国家が主催する展覧会)に出品した《オランピア》です。
準備段階でのデッサンや下絵、画家が参考にしたと思われる過去の絵画作品や写真、さらには、後世の画家がこの作品から刺激を受けて描いた作例など、さまざまなスライドを見せていただいて、一枚の絵の背後に大きな世界が広がっていることを実感できたのではないでしょうか。
しかし、客観的な歴史記述など存在するはずもなく、解釈者の価値観に大きく左右される美術史研究は、常に危うい綱渡りを強いられているのも事実です。先生はたびたび、「この作品にはポテンシャル(潜在能力)がある」、「分析の方法論は選ぶのは作品である」と仰っていました。まず、作品をよく観察し、声なき声に耳を澄ます態度が求められるのでしょう。しかし、作品との対話はなにも専門家だけに許された特権ではありません。
今回の講義に参加した学生が一人でも、二人でも、それぞれの立場で、美術との付き合いが深まっていくことを願っています。
小泉順也(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
6月17日・大石紀一郎先生「歴史の文法と歴史の思想」について
今回は、西洋における歴史に関する思考の変遷を、近代のドイツを中心として思想史の立場から振り返る講義がなされました。
専門的な歴史研究の制度化が始まったのは、それほど昔のことではなく、実は19世紀のドイツにおいて歴史主義と呼ばれる思潮が誕生してからのことでした。歴史主義に先導された歴史研究は、やがて影響力を強めていきますが、それとともにその意義を疑問視するようなさまざまな議論が登場するようになりました。
この講義で取り上げられた議論は、確かに近代ドイツの特殊なコンテクストに密接に結びついたものです。しかし、それらの議論は歴史学の客観性、歴史学の意義、そして歴史学とナショナリズムの関係といった重要な問題に関わっており、私たちが看過することのできないものだと思います。
講義の締めくくりに先生が述べられた「歴史からもはや教訓を学ぶことができなくなった、ということが教訓である。」という言葉は、とりわけ印象的でした。
私たちが、普段何気なく持っている歴史のイメージに揺さぶりを与え、もう一度考え直すきっかけとなるような刺激的な講義だったと思います。
高瀬純平(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
7月1日・今橋映子先生「写真史が生まれる瞬間(とき)─ウジェーヌ・アジェと仏・米現代写真の言説」について
今橋先生は過去にも、この比較日本文化論のテーマ講義で〈パリ写真〉のお話をされてきましたが、今年度は「歴史をどう書くか」というテーマに沿ってフランスの写真家ウジェーヌ・アジェ(1857-1927)を取り上げられました。生前無名だったアジェが、アメリカのシュルレアリスム写真家マン・レイ、ドキュメンタリー写真家ベレニス・アボットを通して世に知られていく際、シュルレアリスム写真の祖、ドキュメンタリー写真の祖として写真史の中に位置づ けられていったというお話を、先生が所蔵されているアジェその他の写真家たちの膨大な写真資料を見ながら聴いていると、まさに「歴史」というものが生成されていく瞬間のドキュメントのように感じられ、とても刺激的なひとときでした。
私個人の関心からもっとも興味を惹かれたのは、〈ドキュメンタリー〉という枠組みがMOMAの写真部長シャーカフスキーによって構築された、というくだりでした。この絶妙な呼び名によって、アジェの写真もその後のフォト・ジャーナリズムの写真も一括りに掬い出されることになったわけですが、この言葉が写真における真偽(「やらせ」)の問題を保留にしたまま一つの言説を作っているという状況は戦略的にも感じられ、今後、新たな言説によって書き換えられる可能性を含んでいるのではないかと思います。
佐々木悠介(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
7月8日・甚野尚志先生「ヨーロッパ史における「王権」の表象 ─教皇の即位儀礼から」について
今回の講義は、中世ヨーロッパにおける教皇の即位儀礼を通して、「王権」の表象を論じるものでした。
従来、わが国では日本の天皇と比肩しうるヨーロッパの王権について論じた場合、教会の首長たる教皇のことを見逃しがちでした。 しかし、甚野先生は、中世においては教皇権がある種の「王権」として理解することが十分に可能であることを、教皇権が古代ローマ帝国の帝権を継承しているとする教会側の主張を可視化した教皇の即位儀礼を中心に見ていくことによって、明らかになさいました。
また、画像や地図などをふんだんに使って、その儀礼が中世初期と、教皇君主政が確立した中世盛期においてはかなりの差異が見られることにも着目し、儀礼の時代性についても論じられました。
聖と俗が不可分であった中世社会というものが、聖権と俗権の両方を併せ持つ教皇の即位儀礼によって可視化されたということも言えるのではないか、と思い、非常に興味深く、また勉強になりました。
長谷川恵(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)
7月15日・瀧田佳子先生「歴史と文学の出会うところ ─日系アメリカ人の文化」について
今回の講義は、日系アメリカ人による文学作品をテキストとして、そこで語られている日系アメリカ人の歴史的経験を振り返るものでした。講義の冒頭で先生がおっしゃったように、歴史と文学を隔てていた境界は、歴史記述の「客観性」への根本的な疑念が広く認識されるようになったことで、ゆらぎ始めています。そうした時代にあって、文学は歴史記述にどのように活かされ得るのでしょうか。
講義で示唆されたひとつの答えは、文学がしばしばマイノリティの声なき声を代弁するものであるという点にありました。それによってマイノリティ文学は、しばしばマジョリティによって語られてきた統一された国民国家の物語の齟齬をつき、新たな歴史記述を生み出す契機を多く含んできたのです。
今回取り上げられた日系人文学の場合、その契機は日米戦争下の強制収容に集約される独自の歴史的経験にあるわけですが、それは一方で幼いマサコが考えたように「私たち(=日系人)の物語」であると同時に、アメリカというより大きな物語の暗い一部でもあり、そこから自由と平等、進歩、民主主義というアメリカ人の好む話題を逆照射して見ることで、アメリカの歴史記述はより深みを持って私たちにせまってくるようになるのではないでしょうか。
深見麻(大学院・比較文学比較文化コース 博士課程)