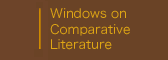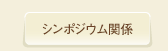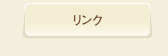『比較文学・文化論集』は、比較文学比較文化研究室所属の大学院生が編集する同人誌で、 創刊されてから既に30 年以上の歴史があり、現在は年1回、3月に刊行するペースで活動しています(発行主体:東大比較文学・文化研究会)。
現在では広く東京大学の学生からの原稿を募集し、文学・芸術・社会・宗教・思想など、「文化」に関する幅広い分野の論文を掲載しています。
『比較文学・文化論集』が目指すのは、既成の学問の枠組みや体制にとらわれない、独創的な研究成果を学生が発表し、互いに刺激を与え合う場として機能することです。これまで発行してきた各号には、いずれも意欲的な論文が集まっており、過去の執筆者には、現在比較文学研究、比較文化研究の第一線で活躍している方が名を連ねています。
本誌に関してご質問のある方、また、最新号およびバックナンバーの購入をご希望の方は、
編集委員会(ronshu @ fusehime.c.u-tokyo.ac.jp)までご連絡ください。
(*アドレスのアットマークを「半角」にしてください。)
最新号・バックナンバーに収録されている論文については、こちらをご参照ください。
『比較文学・文化論集』第 41 号 原稿募集のお知らせ
『比較文学・文化論集』第 41号(2024年3月発行予定)に掲載する原稿を募集いたします。
30年以上の歴史を有する『比較文学・文化論集』は、比較文学比較文化研究室に所属する大学院生が編集する同人誌であり、主目的は学生同士の協力によって論文発表の機会を提供し、活発な議論の場を作り出すことです。
文学・芸術・社会・宗教・思想など、「文化」に関するものであれば分野は特に問いませんが、既成の学問の枠組みや体制にとらわれない、独創的な論考を歓迎いたします。編集委員会では、この雑誌を、様々な分野で研究をなさっている皆さんが、お互いに刺激を与え合うことのできる場にしたいと願っています。
下記の要領で第41号の原稿を募集いたしますので、ふるってご投稿ください。
記
【投稿資格】
次に挙げる 3 つの条件のうち、いずれかに該当する方。
- 東京大学大学院に所属する大学院生と研究生。
- 東京大学教養学部後期課程に所属する学生・研究生。
※学部後期課程の学生・研究生の場合は、指導教官、もしくは論文のテーマに近い分野を専門にしておられる先生に原稿を読んでいただいてから投稿するようにしてください。
- 上記のいずれかに在籍した経歴があり、文化に関する学際的な研究に関心のある方。
【投稿内容】 論文あるいは書評
※今号では、特集企画として「回復とは何か」をテーマとして置いています。
※パンデミックを経て、健康や病いへの関心がこれまでになく高まったと言える今の社会の中で、回復とはどのように考えられるものなのか。多様な分野において考えられてきた「回復」 について、皆様の論考を募集します。ただし、原稿の集まり次第によっては特集とせず、一般論文として掲載する場合がありますので、ご了承ください。
【枚数】
論文の場合、特に制限はありません。
書評の場合は 400 字詰原稿用紙 5 枚から 10 枚程度とします。
【執筆者負担金】
400 字詰原稿用紙 1 枚につき 2,000 円程度(予定)。
(2022年度実績:1400 円程度)
印刷費用に充てるため、各自の執筆枚数に応じた金額を負担していただきます。
【応募申込締切】 2023年 8月 31日
投稿を希望なさる方は、期日までに、氏名・連絡先・投稿内容を電子メールにてお知らせください。
宛先:ronshuhikaku@gmail.com
(*アドレスのアットマークを「半角」にしてください。)
【原稿締切】 2023年 9月 30日必着
【備考】
- 投稿は未発表原稿に限ります。
- 使用言語は問いませんが、編集が困難なものはお断りする場合があります。母語でない言語で執筆する場合は、必ず母語話者のチェックを受けてからご投稿ください。
- 応募時に、予定題目、予定枚数、縦書き・横書きの希望をご連絡ください。
- 応募いただいた方には、執筆要項をお渡しします。表記法等はこれに従ってください。
- 入稿はメールへの添付書類でお願いします。手書き原稿は不可とします。
- 執筆者には完成品を1人最大10部まで差し上げます(郵送先は原則として日本国内の住所に限ります)。抜刷に関しては、別途料金を頂くことで対応いたします。
- 『論集』に掲載された論文の著作権は、本編集委員会に帰属するものとします。なお、著者本人が掲載された論文を他所で使用することを望む場合(例、著書での利用)、本編集委員会の許諾を得る必要はないこととします。
- 『論集』の成果を広く知ってもらうため、東京大学が主催する電子データベース、UTokyo Repositoryへの投稿原稿のアップを予定しています。なお、原則として投稿された原稿は全て、UTokyo Repositoryにて公開させていただく予定ですが、以下の場合はその限りではありません。
・図版等、著作権の問題が生じるものが入る論文を提出される場合。
・執筆者が UTokyo Repository へのアップを希望されない場合。
上記いずれかに該当される方は、個別に対応させて頂きますので、応募時にその旨お伝えください。
以上
『比較文学・文化論集』第 40 号刊行 !!
『比較文学・文化論集』第 40 号が刊行されました。
文学、写真史、音楽学など、『比較文学・文化論集』らしい多岐にわたるジャンルの論考が収められております。
価格は1冊 600 円です。ご希望の方は、下記の編集委員会アドレスまでお問い合わせください。また、東京大学生協駒場書籍部でも販売しています。
目次(一部)
| 王 秋琳 |
中国文学における先鋒派の誕生と程永新
─『収穫』「先鋒小説特集号」 を中心に─ |
| 岡野 宏 |
私は旅行者として話している
─チャールズ・バーニーと聴取の近代性─ |
陳 華栄、陳 多友 |
翻訳から「趣味」へ
—梁啓超と柴四朗の『佳人之奇遇』— |
| 李 範根 |
写真の居場所として「東アジア」を考える
—写真の交差と歴史の分有— |
『比較文学・文化論集』第 39 号刊行 !!
『比較文学・文化論集』第 39号が刊行されました。
文学、哲学、思想史など、『比較文学・文化論集』らしい多岐にわたるジャンルの論考が収められております。
価格は1冊 600 円です。ご希望の方は、下記の編集委員会アドレスまでお問い合わせください。また、東京大学生協駒場書籍部でも販売しています。
追記:2022年に発行されました『比較文学・文化論集』39号所収の論文のうち、一部がUTokyo Repositoryにて公開されました。
この機会にぜひご覧ください。
UTokyo Repository
目次(一部)
| 奥畑 豊 |
精神論の欺瞞
─ J・G・バラード『太陽の帝国』を武士道を通して読む─ |
| 川澄 亜岐子 |
葛藤する僧侶
─ラフカディオ・ハーン「茶の木縁起」と
テオフィル・ゴーチエ「クラリモンド」の関係について─ |
徳永 光展 |
翻訳で読む夏目漱石
—英訳とドイツ語訳を例として— |
| 柳下 壱靖 |
普遍言語の 2 つの相貌
—ジョン・ウィルキンズ『事物記号と哲学的言語にむけての試論』と
17 世紀イングランドにおける言語思想の一側面— |
| 渡邉 京一郎 |
反対気分について |
『比較文学・文化論集』第 38 号刊行 !!
『比較文学・文化論集』第 38 号が刊行されました。
今号では、通常の投稿論文に加え、「〈触れ合えない〉ということ―感染症蔓延下での文化・研究活動を考える―」の特集企画を組みました。
2020年、新型コロナウイルスの影響が世界を蔽った情況に対して、多方面から考察を加えます(明治期の疫病禍、哲学からの考察、演奏会における困難)。
価格は1冊 600 円です。ご希望の方は、下記の編集委員会アドレスまでお問い合わせください。また、東京大学生協駒場書籍部でも販売しています。
目次(一部)
| 佐藤嘉惟・川下俊文・鶴田奈月・皆川梨花・金斗成・田村隆 |
『若草源氏物語』研究ノート―近世俗語訳の諸相― |
| 佐藤 嘉惟 |
早歌《法華》新出断簡の紹介―譜本の装訂・表記体をめぐる試論― |
|
|
| 【特集企画】〈触れ合えない〉ということ―感染症蔓延下での文化・研究活動を考える |
| 高原 智史 |
明治37 年の腸チフス流行と一高自治寮 |
| 山野 弘樹 |
〈触れ合えない〉ということと〈触れ得ない〉もの |
| 石井 萌加 |
コロナ禍の「切り離された」音楽活動を考える |
| |
|
| 岡野 宏 |
触覚的な聴取―グラス・ハーモニカの「病理」をめぐって― |
| 堀江 郁智 |
スティグレールのシモンドンへの言及について―人称の観点から― |
| 山野 弘樹 |
書評 沈黙の言葉―梶谷真司『考えるとはどういうことか』を読む― |
| 山野 弘樹 |
書評 〈世界〉を読むということ―ショウペンハウエル『読書について』を読む― |
『比較文学・文化論集』第 37 号刊行 !!
『比較文学・文化論集』第 37 号が刊行されました。
今号では、通常の投稿論文に加え、「原稿用紙10枚で読む学のあらまし」の特集企画を組みました。日本思想史学、韓国近現代美術史学、歴史哲学に関し、それぞれの「学のあらまし」が「原稿用紙10枚」のサイズでまとめられています。
価格は1冊 600 円です。ご希望の方は、下記の編集委員会アドレスまでお問い合わせください。また、東京大学生協駒場書籍部でも販売しています。
目次(一部)
| 高原 智史 |
学生が雑誌をつくるということ |
| 厳 教欽 |
『能因法師集』における古歌の受容 |
| 金 有珍 |
立教大学図書館蔵『月光花光草子』の紹介・翻刻 |
| |
|
| 【特集企画】原稿用紙10枚で読む学のあらまし |
| 高原 智史 |
古典に向かう愛と論理――日本思想史学の方法論としての「フィロロギー」について |
| 南 希宙 |
韓国近現代美術史――民族主義的な学問分野の再構築 |
| 山野 弘樹 |
歴史・メディア・表象――テッサ・モーリス=スズキ『過去は死なない』を読む |
| |
|
| 山野 弘樹 |
「ヒストリオロジー」の可能――歴史と哲学の対話に向けて―― |
| 建部 良平 |
人情と科学の哲学者:戴震及びデイヴィッド・ヒュームの比較可能性についての試(私)論 |
| 渡邉 京一郎 |
世界によって退屈させられるということ──退屈の第一形式とはなにか |
| 石井 萌加 |
「北方的」ブラームス像とドイツのナショナリズム |
| 高 薇 |
古代日本における『文選』の学術的側面——『文選』の注を手がかりに—— |
| 陳 華栄 |
梁啓超の朝鮮観と『佳人奇遇』 |
第 37 号編集委員会
問い合わせ ronshu @ fusehime.c.u-tokyo.ac.jp
『比較文学・文化論集』第 36 号刊行 !!
『比較文学・文化論集』第 36 号が刊行されました。
今号では、通常の投稿論文に加え、「世界文学」の特集企画を組みました。
価格は1冊 600 円です。ご希望の方は、下記の編集委員会アドレスまでお問い合わせください。また、東京大学生協駒場書籍部でも販売しています。
目次
| 徳永 光展 |
定年退官という残酷――山崎豊子『白い巨塔』にみる東貞蔵教授の胸中 |
| 川下 俊文 |
狩野良知『三策』の成立と書誌 |
| |
|
| 【特集企画】世界文学 |
| 伊藤 徳也 |
「世界文学」と「世界文学史」 |
| 佐藤 光 |
世界文学に対する一つの態度――「言葉のお守り的使用法」を手掛かりに |
| 宮下 華 |
世界文学試論 |
| Rachel QUAH |
A Metropolitan Utopia |
| |
|
| 陳 華栄 |
『佳人奇遇』と『十五小豪傑』の翻訳意図に関する比較研究 |
| 梁 蘊嫻 |
『三国志演義』における日本語の翻訳――小川環樹・金田純一郎訳『完訳三国志』を中心に |
| 奥畑 豊 |
冷戦の終わりに――ジュリアン・バーンズ『ポーキュパイン』とイアン・マキューアン『黒い犬』について |
| 桑原 旅人 |
森敦『月山』における「ファルス的享楽」――ジャック・ラカンの理論に依拠した精神分析批評 |
| 榊原 知樹 |
Melancholy and a Tower of Solitude: Robert Burton and Michel de Montaigne |
| 山本 千寛 |
書評 Spatial Ecologies: Urban Sites, State and World-Space in French Cultural Theory (Verena. A. Conley, Liverpool University Press, 2012) |
| 山野 弘樹 |
歴史の「物語論」を考え直す――『物語の哲学』における「歴史の反実在論」を中心に |
| 佐伯 綾希 |
ウンベルト・ボッチョーニ《ベアタ・ソリトゥード・ソラ・ベアティトゥード》におけるヴァティカンとモデルニズモ |
| 河村 龍廣 |
アブドゥラウフ・フィトラトの『ウズベク古典音楽とその歴史』とそのソビエト音楽学との関係 |
第 36 号編集委員会
問い合わせ ronshu @ fusehime.c.u-tokyo.ac.jp