|

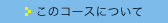
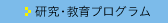
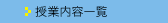
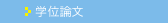
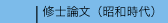
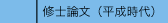
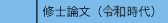
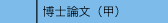
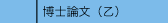
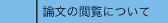
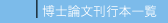
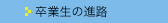
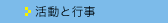
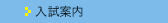

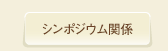
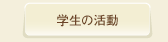
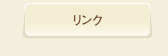
Copyright 2006 © All rights reserved by
The University of Tokyo
|

令和6/2024年
| 権保慶 |
『抒情のアイデンティティ―金素雲『朝鮮詩集』と金時鐘『再訳朝鮮詩集』』東京大学出版会 |
| 木瀬康太 |
『キェルケゴール美学私考―イロニーと良心』北樹出版 |
| 李太喜 |
『自由と自己の哲学―運と非合理性の観点から』岩波書店 |
| 梶野絵奈 |
『ヴァイオリンを弾き始めた日本人―明治初年、演奏と楽器製作の幕開け』青弓社 |
令和5/2023年
| 神林尚子 |
『幕末・明治期の巷談と俗文芸 女盗賊・如来の化身・烈女』花鳥社 |
令和4/2022年
| 梶野絵奈 |
『日本のヴァイオリン史 楽器の誕生から明治維新まで』青弓社 |
令和3/2021年
| 岩下弘文 |
『ふわふわする漱石―その哲学的基礎とウィリアム・ジェイムス』東京大学出版会 |
| 趙怡 |
『二人旅 上海からパリへ―金子光晴・森三千代の海外体験と異郷文学』関西学院大学出版会 |
| 松枝佳奈 |
『近代文学者たちのロシア―二葉亭四迷・内田魯庵・大庭柯公』ミネルヴァ書房 |
| 二村淳子 |
『ベトナム近代美術史 フランス支配下の半世紀』原書房 |
| 山本嘉孝 |
『詩文と経世 ― 幕府儒臣の十八世紀』名古屋大学出版会 |
令和2/2020年
| 堀江秀史 |
『寺山修司の一九六〇年代-不可分の精神』白水社/『寺山修司の写真』青土社 |
平成31・令和1/2019年
| 松尾梨沙 |
『ショパンの詩学-ピアノ曲《バラード》という詩の誕生』みすず書房 |
| 金志映 |
『日本文学の〈戦後〉と変奏される〈アメリカ〉-占領から文化冷戦の時代へ』ミネルヴァ書房 |
| 李賢晙 |
『「東洋」を踊る崔承喜』勉誠出版 |
| 飯嶋裕治 |
『和辻哲郎の解釈学的倫理学』東京大学出版会 |
| 田中有美 |
『生きてゆくドン・キホーテ-日米現代小説における非ロマン主義的受容』晃洋書房 |
平成30/2018年
| 中井真木 |
『王朝社会の権力と服装 直衣参内の成立と意義』東京大学出版会 |
| 大西由紀 |
『日本語オペラの誕生-鴎外・逍遙から浅草オペラまで』森話社 |
| 柳忠熙 |
『朝鮮の近代と尹致昊-東アジアの知識人エトスの変容と啓蒙のエクリチュール』東京大学出版会 |
平成29/2017年
| 笠原賢介 |
『ドイツ啓蒙と非ヨーロッパ世界-クニッゲ、レッシング、ヘルダー』未来社 |
アダム・
カバット |
『江戸化物の研究 草双紙に描かれた創作化物の誕生と展開』岩波書店 |
| 裵寛紋 |
『宣長はどのような日本を想像したか-『古事記伝』の「皇国」』笠間書院 |
平成28/2016年
| 柴田真希都 |
『明治知識人としての内村鑑三-その批判精神と普遍主義の展開』みすず書房 |
| 佐々木悠介 |
『カルティエ=ブレッソン-二十世紀写真の言説空間』水声社 |
| 松居竜五 |
『南方熊楠-複眼の学問構想』慶應義塾大学出版会 |
平成27/2015年
| 菊池有希 |
『近代日本におけるバイロン熱』勉誠出版 |
| 韓正美 |
『『源氏物語』における神祗信仰』武蔵野書院 |
| 金子美都子 |
『フランス二〇世紀詩と俳句-ジャポニスムから前衛へ』平凡社 |
平成26/2014年
| 川島健 |
『ベケットのアイルランド』水声社 |
| 南相旭 |
『三島由紀夫における「アメリカ」』彩流社 |
| 手島崇裕 |
『平安時代の対外関係と仏教』校倉書房 |
平成25/2013年
| 池田美紀子 |
『夏目漱石 眼は識る東西の字』国書刊行会 |
| 鄭玹汀 |
『天皇制国家と女性-日本キリスト教史における木下尚江』教文館 |
| 金成恩 |
『宣教と翻訳-漢字圏・キリスト教・日韓の近代』東京大学出版会 |
| 泉美知子 |
『文化遺産としての中世-近代フランスの知・制度・感性に見る過去の保存』三元社 |
平成24/2012年
| 渡辺邦夫 |
『アリストテレス哲学における人間理解の研究』東海大学出版会 |
| 平石典子 |
『煩悶青年と女学生の文学誌-「西洋」を読み替えて』新曜社 |
デンニッツァ・
ガブラコヴァ |
『雑草の夢-近代日本における「故郷」と「希望」』世織書房 |
| 加藤百合 |
『明治期露西亜文学翻訳論攷』東洋書店 |
平成23/2011年
| 鈴木淳子 |
『ヴァーグナーと反ユダヤ主義-「未来の芸術作品」と19世紀後半のドイツ精神』アルテスパブリッシング |
| 牧野陽子 |
『〈時〉をつなぐ言葉-ラフカディオ・ハーンの再話文学』新曜社 |
平成22/2010年
| 川口恵子 |
『ジェンダーの比較映画史-「国家の物語」から「ディアスポラの物語」へ』彩流社 |
平成21/2009年
| 山中由里子 |
『アレクサンドロス変相-古代から中世イスラームへ』名古屋大学出版会 |
| 陳岡めぐみ |
『市場のための紙上美術館-19世紀フランス、画商たちの複製イメージ戦略』三元社 |
平成20/2008年
| 金沢百枝 |
『ロマネスクの宇宙-ジローナの〈天地創造の刺繍布〉を読む』東京大学出版会 |
平成18/2006年
| 鈴木禎宏 |
『バーナード・リーチの生涯と芸術—「東と西の結婚」のヴィジョン』ミネルヴァ書房 |
| 戸田勝久 |
『武野紹鴎 茶と文藝』中央公論美術出版 |
| 大東和重 |
『文学の誕生-藤村から漱石へ』講談社選書メチエ |
平成17/2005年
| 金沢英之 |
『宣長と『三大考』—近世日本の神話的世界像』笠間書院 |
| 西槇偉 |
『中国文人画家の近代—豊子愷の西洋美術受容と日本』思文閣出版 |
| 藤田みどり |
『アフリカ「発見」—日本におけるアフリカ像の変遷』(世界歴史選書)岩波書店 |
平成15/2003年
| 西原大輔 |
『谷崎潤一郎とオリエンタリズム—大正日本の中国幻想』中央公論新社 |
平成14/2002年
| 金原禮子 |
『フォーレの歌曲とフランス近代の詩人たち』藤原書店 |
| 松井貴子 |
『写生の変容─フォンタネージから子規、そして直哉へ』明治書院 |
テレングト・
アイトル(艾特) |
『三島文学の原型—始源・根茎隠喩(ルートメタファー)・構造』日本図書センター |
平成13/2001年
| 牛村圭 |
『「文明の裁き」をこえて—対日戦犯裁判読解の試み』中央公論新社 |
| 秋山学 |
『教父と古典解釈 予型論の射程』創文社 |
ツベタナ・
クリステワ |
『涙の詩学—王朝文化の詩的言語』名古屋大学出版会 |
平成12/2000年
林容澤
(イム・ヨンテク) |
『金素雲「朝鮮詩集」の世界—祖国喪失者の詩心』中央公論新書 |
| 宮本久雄 |
『他者の原トポス—存在と他者をめぐるヘブライ・教父・中世の思索から』創文社 |
| 山本巍 |
『ロゴスと深淵—ギリシア哲学研究』東京大学出版会 |
平成11/1999年
| 張偉雄 |
『文人外交官の明治日本—中国駐日公使団の異文化体験』柏書房 |
成恵卿
(ソン・ヘギョン) |
『西洋の夢幻能—イエイツとパウンド』河出書房新社 |
平成10/1998年
| 佐伯順子 |
『「色」と「愛」の比較文化史』岩波書店 |
| 榎本泰子 |
『楽人の都・上海—近代中国における西洋音楽の受容』研文出版 |
平成9/1997年
| 小谷野敦 |
『〈男の恋〉の文学史』朝日選書 |
| 中村都史子 |
『日本のイプセン現象 1906-1916』九州大学出版会 |
平成8/1996年
| 井上忠 |
『パルメニデス』青土社 |
| 上垣外憲一 |
『ある明治人の朝鮮観—半井桃水と日朝関係』筑摩書房 |
平成7/1995年
| 張競 |
『近代中国と「恋愛」の発見—西洋の衝撃と日中文学交流』岩波書店 |
| 福田眞人 |
『結核の文化史—近代日本における病のイメージ』名古屋大学出版会 |
平成6/1994年
尹相仁
(ユン・サンイン) |
『世紀末と漱石』岩波書店 |
| 新田義之 |
『リヒアルト・ヴィルヘルム伝』筑摩書房 |
| 佐々木英昭 |
『「新しい女」の到来—平塚らいてうと漱石』名古屋大学出版会 |
平成5/1993年
| 杉田英明 |
『事物の声 絵画の詩—アラブ・ペルシャ文学とイスラム美術』平凡社 |
| 今橋映子 |
『異都憧憬 日本人のパリ』柏書房 |
平成3/1991年
| 川本皓嗣 |
『日本詩歌の伝統—七と五の詩学』岩波書店 |
| 劉岸偉 |
『東洋人の悲哀—周作人と日本』河出書房新社 |
| 厳安生 |
『日本留学精神史—近代中国知識人の軌跡』岩波書店 |
昭和62/1987年
昭和59/1984年
| 芳賀徹 |
『絵画の領分—近代日本比較文化史研究』朝日新聞社 |
昭和52/1977年
| 太田雄三 |
『内村鑑三-その世界主義と日本主義をめぐって』研究社出版 |
昭和46/1971年
| 平川祐(祐)弘 |
『和魂洋才の系譜—内と外からの明治日本』河出書房 |
昭和45/1970年
| 亀井俊介 |
『近代文学におけるホイットマンの運命』研究社 |
昭和44/1969年
|