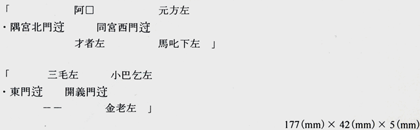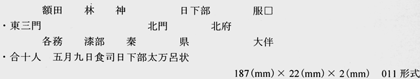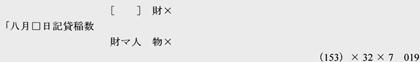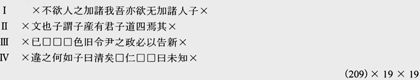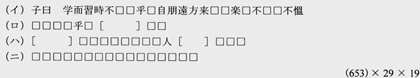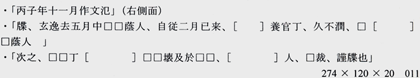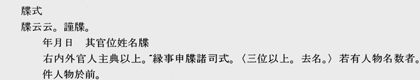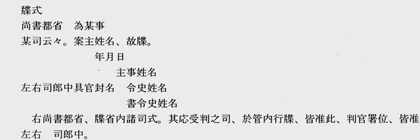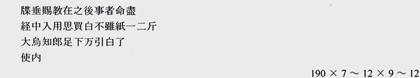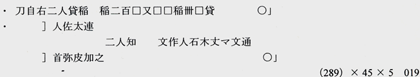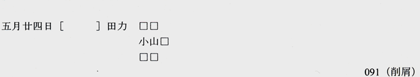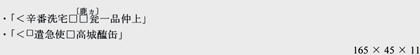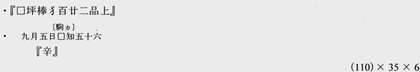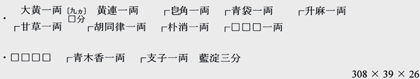断面三角形の棒状の木片の二面に墨書がある。文字のない面は、「大黄」で始まる面と同じくらいの幅があり、「青木香」の面よりも広い。下端は刃物による調整が行われているようである。
書式についてみると、薬物名を列挙してその下に一両、三分などの重量を記している。また、大部分の薬名に合点を施している。
当初、一つの面に2行書きで薬物名を書いたものの、一つの面では間に合わず、別の面に残りの薬物名を1行書きしたものと思われる。
釈読作業の過程で参考となったのは、正倉院の北倉に伝わる「種々薬帳」である(『大日本古文書』4-171)。この「種々薬帳」は、聖武天皇の七七日忌にあたる天平勝宝八歳(756)六月二十一日に、追善供養のために光明皇后が東大寺大仏に献上した薬物を記録したもので、「国家珍宝帳」とならぶ献物帳の一つである。
雁鴨池出土木簡に記載されている薬物名の多くが、この「種々薬帳」に記載されている薬物と共通している点が、注意をひく。具体的には、木簡にみえる「大黄」「甘草」「朴消」「黄連」「胡同律」などが、「種々薬帳」にも登場する。
また、「青木香」については、正倉院文書の天平宝字六年(762)閏十二月二日「奉写二部大般若経料雑物収納帳」(『大日本古文書』16−125)に、「薫陸一両青木香五両雑香参両」を買ったという記載がみえており、同時代の日本にも存在したことが確認できる。
このように、8世紀の新羅と日本で、共通の薬物が数多く登場している点は示唆的である。これは、同時期(8世紀)の新羅と日本で、薬物の名称や知識が共有されていたことを示しているのではないだろうか。
これに関連して、「種々薬帳」には「新羅羊油」という薬物名がみえるのも興味深い。雁鴨池出土木簡の薬名木簡の発見は、日本への薬物(やそれにともなう知識)の伝来ルートについても示唆を与えるのではないだろうか。
さらに注目されるのは、雁鴨池出土の薬名木簡は、薬物名の列記のほかに、なにかのチェックに用いた際の合点が付されている。尹善泰氏がすでに指摘しているように、これとほぼ同様の書式が、正倉院の北倉に残る「雑物出入継文」の中の、天応元年八月十六日の「造東大寺司請薬注文」にみえる。合点の付し方などが酷似しており、雁鴨池出土の薬物名木簡も同様に薬物の出納に関わって機能していたことを示していると考えられる〔尹善泰2007〕。
この木簡の機能について尹善泰氏は、処方箋に関するものと推定している。これに関連して、天平9年(737)の疫病の際に出された典薬寮勘文(『朝野群載』巻21、凶事)には、傷寒にともなう豌豆病(天然痘)の治療法として、「初発覚欲作、則煮大黄五両服之」「又青木香二両、水三升、煮取一升頓服」「又黄連三両、以水二升煮取八合、服之」などとあり、薬物の摂取に必要な分量が記されている点は注目される。本木簡にみえる「両」単位の記載は、こうした治療法と関わるものかもしれない。
薬物名木簡の発見は、以下のような意義を有している。
第一に、朝鮮半島の医薬文化と日本との関係である。この点に関してはすでに東野治之氏が、古代日本の医学については、唐の影響下での医疾令受容という面だけでなく、朝鮮系の医薬文化の受容を視野に入れるべきであると注意を喚起しており〔東野治之1999〕、本木簡は、それを具体的に示す事例であるといえる。
ひるがえってみれば、これまでの文献史料の中にも、日本の医薬文化が朝鮮半島と深く関わっていることを示唆する記事が数多くみられる。例えば、古くは『日本書紀』允恭天皇紀3年春正月朔条に「使を遣わして良き医を新羅に求む」、同年秋8月条に「医、新羅より至れり。則ち天皇の病を治めしむ」とある。これらは医薬文化をめぐる朝鮮半島との関係を意識した記述であることには相違ない。また、欽明天皇15年2月条に、百済から易博士、暦博士らとともに「医博士」「採薬師」が渡来したとする記事があるのもよく知られている。
さらに『続日本紀』天平宝字2年(758)4月己巳条によれば、医療系官人であった難波連奈良の遠祖徳来は、もと高麗の人で百済国に帰していたが、雄略天皇が百済国に才人を求めたときに貢進され、その後、その五世の孫恵日が唐で医術を学んだとあり、難波連奈良が半島系の渡来人の系譜をひく人物であったことがわかる。このほかにも、奈良時代の医薬系官人の中に、葛井連恵文といった半島からの渡来人とみられる人物もみえる。
本木簡により、8世紀の新羅における医薬文化の一端をかいま見られた意義は大きい。これまで必ずしも明らかではなかった、医薬文化をめぐる半島と列島との関係を、具体的な形で示したものといえよう。
第二に注目したいのは、雁鴨池出土木簡で使われているさまざまな語が、同時期の日本の正倉院文書にも少なからずみえており、木簡の解釈や評価を行う上で、きわめて有効であると考えられることである。そしてそのことは同時に、8世紀の新羅と日本で、物質文化や文字文化をかなりな程度共有していた事実を示しているに他ならない。
8世紀以降の正倉院文書に代表される文字文化と、同時期の新羅の文字文化についても、今後さらに比較を進めていく必要があるだろう。 |
![]() © 2007-2011 The University of Tokyo
© 2007-2011 The University of Tokyo