1.陵山里寺址(「陵寺」)
2000年から2002年にわたった発掘で、寺院南側にあるY字の初期自然排水路から計27点の木簡が出土した。木簡出土層の復元と解釈において発掘者の間に、567年の寺院建立以前という解釈と、その後という解釈に分かれている。これに基づいて扶余遷都前になされた羅城築造やあるいは寺院建立以前に築造された羅城城門の禁衛と関連づける解釈と、554-567年の間と見る解釈、そして寺院建立以後と見る解釈が並立している。木簡の内容が寺院と関係のあることからして、完全に寺院を取り外しては議論しがたいところがある。
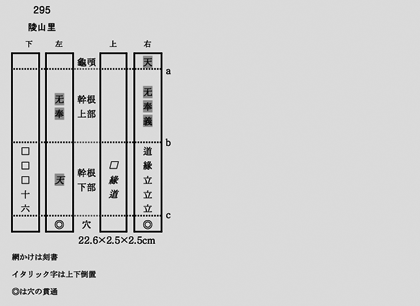
[以下、図はすべてクリックすると別ウィンドウで大きく表示されます]
男根形の木材品に刻書と墨書がある。勃起した男根がリアルに描写されている。亀頭部分は表現されたが、嚢心部分は省略された代わりに、尖頭形の貫通した穴がある。男根の幹根部分を非常に長く誇張して表現しており、これは文を書くための空間を確保するためのものと見られる。亀頭の姿を基準として上下左右を区分することができる。字の正置と倒置関係からして、右面と下面が一組になり、さらに左面と上面が一組になる。
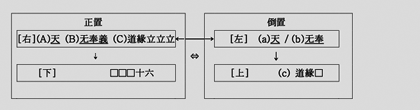
対応関係をなす右面と左面は、刻書のある点とその内容が互いに類似している。内容上、(A)=(a)、(B)=(b)、(C)=(c)と対応する。すなわち、正置された右面・下面組と倒置された左面・上面組は相互対蹠関係である。
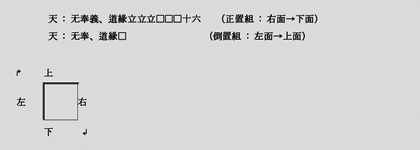
刻書したことには特別な意味があるように考えられる。「无」は仏経に見える書体である。「无」にはまた反語法的に「‐しないだろうか」という用法があり、仏経を暗誦する際に使われる発語辞でもある。「无奉義」は「義を奉ずる」という意で解釈しておく。「无奉」は「无奉義」の縮約形であろう。「道縁」は「道のはた」あるいは僧侶の名前と見られる。「立」は「立てる、立つ」という意味とともに男性性器の「勃起する」という意味もある。「立」字のある右面を含んだ正置組は、亀頭が空に向かっていて勃起した男根の姿に一致する。「立立立」と3回繰り返したことは強調と見られるが、念願を込めた呪文のように思われる。「天」は天神を意味するより、男根方向の上下を表示しているのではないか。 「道縁」を「道のはた」とするならば、道神との関連を重視することもできる。既に日本の道饗祭・道祖神と関連づける説がある。すなわち百済王が常住する都城の入口の施設で、門柱のようなところにぶら下げておくことによって(「道縁立」)、都城の外側から邪気が入るのを防ぐ、呪術的な役割を遂行したと見るのである。
字の方向からして、木簡の4面のうち正置組を基準とすれば、亀頭を空へ向かって男根を勃起状態に立てるか、倒置組を基準として発起していない状態で下に落とす、二種類の局面が演出されたと推定される。
従来、百済地域に知られている男根表象は、百済地域土着の祭事や呪術と関連が深い。扶余郡九龍面東方里論峙出土、馬韓時代の祭祀遺跡においても土器の取っ手の部分を男根で表し、百済時代の宮南池でも木製男根が出土した。江原道・三陟神南里海神堂の男根信仰をはじめとする東海岸の男根信仰は、女神に対して男根を削って捧げたり雄牛の嚢心を供え物として捧げたりしている。「奉義」「奉」という文句を見れば、奉献された対象は他ならぬ、この木製男根である。
また、本木簡は寺院の中門址の南側水路で発見されたが、これは寺院との関連のなかで使用・廃棄されたことを意味する。忠北・報恩所在の俗離山法主寺に、仏教仮装劇の郡守吏房という遊びがあるが、ここでは木棒で陽茎を形容し、それを持ち上げて神を慰安したという。これは後代のことではあるものの、仏教寺院で木製男根が奉献された事例として陵山里の場合と同じである。すなわち男根は悪鬼を追い出したり神に捧げたりするものであり、旺盛な生殖力と活気ある生命観を依託する対象でもあった。
この男根型木簡ないし木製男根は、寺院建立前後に陵寺に奉献されたものと見られる。これは男根の生殖力・生命力をもとに邪悪な鬼神と気勢を慰撫または威嚇し、邪気が聖域寺院に近づかないようにするためのものだったであろう。泗沘時代(538-660年)の百済には呪文・符呪などを使って邪気を払い病気を治す、一種の精神心理治療師である呪噤師が存在した。元来中国における呪噤は仏教で始まって道教でも盛んであり、百済の呪噤師は仏教を媒介として受容されたものと考えられる。男根型木簡は寺院で行われた呪噤行為の一環として理解される。
陵寺建立の目的は新羅との戦いで戦死した聖王の冤魂を慰め追福するためであった。国王の聖王をはじめ、佐平4人、兵卒2万9千6百人が戦死し、百済の朝野に及ぼした衝撃は相当なものであった。太子の昌(後の威徳王)が直ちに即位できず猶予期間を置かねばならなかったことと、彼が即位した後にも父王聖王のための舎利供養の主体になれなかったことから当時の雰囲気が窺える。聖王をはじめとする戦死者の魂とその家族らと民心を安定させる、一大パフォーマンスの中心に陵寺があり、男根型木簡もまさに同じ脈絡で理解できる。戦死した霊に対する慰安と、生命力の再生、そして二度と百済に邪悪な気勢が宿らないようという念願を込めて男根型木簡が陵寺に奉献されたのではないか。このような土着信仰に基づき、あるいは道教思想との関連をも考えられる、男根信仰の呪術的行為が仏教寺院で行われたということは、当時の百済仏教の性格を察する上で重要であろう。
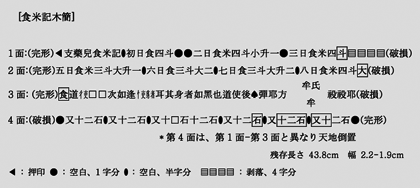
1面、2面は「支薬児食米記」である。これは「薬児の食米を支給した記」、ないし「薬児を扶支する食米の記」と解くことができる。「食」は韓国古代の関連文字資料の用法からして「ご飯」「食べ物」と解される。一方、日本の古代木簡のなかにも食米関連木簡の例を見られるが、それらは「食料支給」を意味する。「記」は記録・帳簿を意味する。「薬児」は「薬の調剤と処方および薬剤などの薬関連業務従事実務者」と見える。「薬児」という表記と関連し、中国唐制の「薬童」が注目される。唐制の「薬童」とは主薬や典薬の補佐役で、尚薬局や奉医局などで医薬の調剤と処方、薬剤管理を担当した実務者であったとされる。韓国古代には「児」が選好・多用された痕跡があり、職制に見える「児」は「童」にも通じる。これは子供という意味よりは、キャリアの少ない末端実務者を象徴するのであろう。これを内容別・日付別に整理すれば、次の通りである。
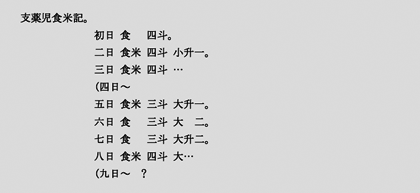
記録の題名の下に「日+食(米)+数量」との書式で列記されている。「食米」は「食」とも、また「大升」は「大」とも省略表記されている。日付は第1面に1、2、3日が見え、第2面に5、6、7、8日が見える。
第1面と第2面の末尾は破損している。第2面の内容からして少なくとも1-2字はあったはずであり、換算すれば46.4cm、これが本木簡の最小値となる。26字が入っている第1面は、上から38.1cmの部分まで空格を含んで、29字分を想定できる。入り得る最大限の内容を前提にすれば55.2cmとなり、これが本木簡の最大値である。つまり、本木簡の本来の長さは46.4cm~55.2cm程度と推定される。この長さを勘案すると、あえて空白にした場合でない限り、「四日」と「九日」に対する記録があったことはほぼ確実であろう。木簡の記録単位からすれば、第8日または第9日が記録の一単位をなしている。
そして、穀物すなわち米の単位、石・斗・大升・小升が見える。1石=10斗=100升とは通時代的な認識であったが、大升・小升は時代によって少し違いがあり、中国では漢代には少升は1/3升、大升は2/3升であり、唐代には大升は3升であった。ところで、食米の支給量は概して日付ごとに4斗が上がり下がりしており、漢代の小升や大升の基準では説明がつかない。まずは「10升=1斗」が大前提になり、「1小升≦1升<1大升<2大升<10升(=1斗)」
の前提が成立する。よって「大升<5升」となり、「1大升≦1/3斗=3.33升」を想定することができる。つまり、1大升は3.33升以下となる。連動する小升は升と違い、想定しがたい。資料の増加を待つべきだが、小升1は1升と同じものと想定せざるを得ない。要するに、本木簡で穀物「10升=1斗、大升1≦3.33升、小升1=1升」という式が想定される。これは唐代の大升と同じである。
第3面は、その内容上の構成が複雑である。

右辺に「吏」をもちながら、左辺が「彳」(第3字)「忄」(第8字)「イ」(第18字)である字が見られる。第18字は疑いなく「使」である。第3字は「彳吏」だが、「使」と見て良いだろう。第8字は「忄吏」と見て、「使」の異体字の範疇に入れておくことができる。この場合、「使」に対して二つほどの異体字が想定される。これらは「吏」、すなわち「官吏」の範疇であり、「道使」とともに羅列されている点から、地方官である道使系列の官吏と推定することもできる。「豸者」は字典には見られないものの、「豬」「猪」の異体字であろう。「弾耶方」は「方」という語彙からして、恐らく百済の地方行政単位である。「道使」の次には、古代金石文一般の傾向から人名がくるだろうと推定される。以上を前提とすれば、次のように区切って読むことができる。
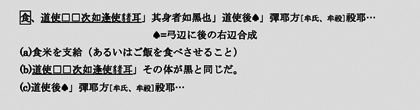
下線部は様々な解釈が可能だが、概して「職責+名前」の構造と見ることができる。「弾耶方」は、百済の地方制度の最も上位に位置する「五方」のそれとは違う。割註の用法からして「弾耶方」があり、「牟氏、牟祋」はそこに所属しているものであろう。同用法は同じ陵寺で出土した木簡304の「宝憙寺[智真、慧×]」においても確かめられる。郡県の長である「道使」が羅列され、次に地方行政区域と見られる「方」が羅列されているのは、まず地方の長の道使級の人名が羅列された後、続いて道使と関連した地方名が羅列されたことと判断される。
第1面と第2面は連続する一つの文書であることに間違いない。第3面の第1字「食」が確実であり、第1面と第2面が連動するものであれば、第3面は、食料の支給対象者である食口の名簿となるわけである。「豸者耳」は人名でなく、「豚」の表記という説もある。その場合、以後の叙述は黒豚を指すこととなる。地方の特産物ないし薬剤としての黒豚を想定することもできる。第3面をこのように錯綜した文章と捉えるのであれば、習書と見る余地もある。第4面は「又十二石」の反復であり、第1面・第2面・第3面と天地が逆になっている。これにより第4面を習書と判断することもできる。ただしそれなりの意味のある記録ならば、「又」が集計上では足すことを意味するという面で、統計にかかわる記録や計算とも考えられる。
いずれにせよ、この記録は薬部・薬児の薬材収集・受納と想定される。よって、ここで行われた会計支出および集計も、やはりそれにかかわった業務から派生したのであろう。百済の医薬の高い水準は中国史書にも伝わっており、独自の医薬書もあったとされるほどである。

これは名簿と見られる独特の木簡である。「攵」は珍しいが、「久」「父」「文」と読むこともできる。他の部分は完全な形だが、縦面の左側は破損している。本来左側に2行があったろうと推測される。上部は三角形に近い梯形である。「‐貴」「‐文」「‐牟」は『日本書紀』などの百済関連人物の人名にしばしば見られる用字であるため、全体的に人名の羅列と考えられる。現在残っているのは10個の名前だが、本来は18個だったと見られる。裏面は「巛」のような記号を7行ほど羅列している。表面は墨でマス目を作り、裏面は枠の線を引いている。陵寺出土の他の木簡とは異なり、厚さが非常に薄い。紙の代用であって、まるで紙のように使われた文書であった可能性がある。因みに薄さで言えば、日本や中国の祭事に使われる人形模様の木製品のそれとも類似しており、裏面の記号は呪術的な感じもする。正確な用途は断定しがたく、この木簡は人名簿の記録簡として行政に使われたものか、呪術的な呪符木簡だったろうと想定しておき、今後資料の増加を待つこととする。
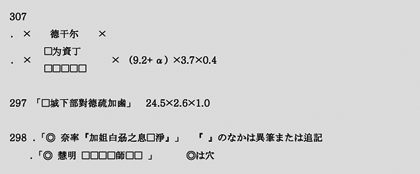
307の「‐徳」は、百済の官等16等のうち、第7位から第11位までにつく接尾辞である。実際に297木簡にも「対徳」が見られる。「干尓」(ないし干尓…)は名前だろう。「資丁」という用語が注目される。日本古代の「資人」は、国家が貴族の家に支給し、そこで奉仕させた従者で官僚制の末端に位置する。50戸ごとに2人ずつ3年交代で派遣し、その生活費は故郷に負担させた制度があったが、「仕丁」とはこれらの地方から派遣され都城の官司で雑役に従事していた者である。「資丁」とはこうした地域で役の一つとして派遣され、宮内・官司や貴族のもとで雑役に従事した役職を指すと推定される。
297、298は、「(出身地または居住行政区域名+)官等+人名」という書式をもつ木簡である。「対徳」は官等第11位であり、「奈率」は第6位である。「疏加鹵」「加姐」「白刕…」「慧明」は人名と考えられる。とくに「慧明」は僧侶の名前のようであるが、これは「師」にも相応しい。中級貴族に伴い、雑役従事者、そして僧侶が陵寺にかかわる工事・事業・行事に関与していたことを示唆する。
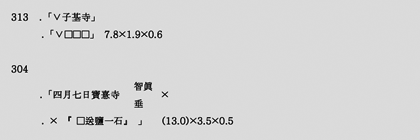
313は上段に切り込みが彫られている典型的な付札・荷札である。304は4月8日の釈迦誕辰日行事にかかわって、宝憙寺から陵寺の現場に運ばれてきた物品の荷札である。「智真」などは宝憙寺所属の僧侶と見られる。裏面は異筆である。木簡とともに陵寺に送付されてきたのは塩1石だった。上記宝憙寺や子基寺は陵山里にあった寺の名前だったとは考えがたく、周辺の寺であったろう。陵寺の行事や事業に関連し、これらの寺から塩のような物資の授受・収斂が行われている。宝憙寺の場合は表面と裏面との間に書記の時差が見える。この時差をいかに見るかにより、いくつかの想定が可能だが、概ね宝憙寺から陵寺へ塩を送付したと見て無難であろう。寺院間のネットワークが機能しており、王室寺院としての位相を示している。ここに22部官舎のうち、寺院と仏法を担当したとされる功徳部の関与をも推定できる。

296は「梨田」の次の部分を削って、もう少し大きい字で異筆追記したものである。「月」偏の字らを羅列していることから、その系列の字の習書と考えられる。裏面も同様である。本来、3月12日の梨田などにかかわった生産品・麦などに関連のある記録であったものが、記録としての用途が完了し、習書として再利用されたのである。「月」偏の字である「脳」「脛」など、身体関連用字がほとんどである。これを習書した主体は医薬関連者であった可能性がある。梨田から出る梨は薬材として活用されたのである。本草綱目や類聚によると、梨は中風で喉がかれた時、熱を下げたり胸が苦しい時に使ったりした薬剤であった。なお、升麻の場合も、その根幹は解熱、腫毒、痔疾、害毒、小児尿血、偏頭厭などの薬剤として使われた。
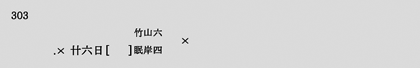
竹山から出る竹も薬として使われていた。竹実は精神を良くし、胸苦しさに利き、体を軽く感じるようにするなど、気勢を助ける。また、竹根は煮詰めて食べれば、虚を補い、気を下げ、風病を治すという。竹茹の薄い内皮である青皮は、吐き気やしゃっくりを止め、肺病で血を吐く病気を治す。竹黄、すなわち竹の節のなかにある黄色がかった白い物質は、鉱物性薬剤を解毒し熱を下げる。
つまり、この一連の木簡を通じて、竹山・梨田のような農園が存在しており、その供給する用途は様々であったにせよ、とりわけ薬材との関連の深かったことが分かる。3月なら梨田に種まきして栽培する時期である。「竹山六」という語からして、竹を植え栽培する山が6個という意味であろう。したがって、これらは何月26日に竹栽培山の農園の数を記録したものと捉えられる。それを管掌する機関が薬部だったとすれば、農園は薬園でもあったはずである。百済の医薬分野は倭においても評価されており、こうして栽培・採取された薬物は医薬関連専門家とともに倭に輸出されたりもした。前掲薬児木簡と関連づけてみると、薬園に対しては関係機関、すなわち薬部により定期的に一定期間点検が行われていた。具体的に、薬児ら約20人余りが動員され、約10日にわたって作業が行われていたと見られる。
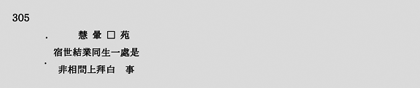
305木簡は4-4句の形式であるが、百済で4句は珍しくない。沙宅智積碑は4-6駢儷体であり、日本にも伝えられた千字文は4-4句である。このように本木簡は詩経・書経などの経書体・千字文体と言える。解釈は次のようにできる。
宿世(=前世)に業を結んだから、[現世に]共に同じところに生まれた。
これは互いに尋ねた(計算した)ことではありません。謹んで申し上げます。
「宿世」「結業」「同生一処」は仏経的用語である。仏経に対する知識を熟知していた人の書いた文章である。「慧暈」は僧侶であろう。仏教と木簡とのつながりは、出土地が陵寺という点を考えれば当然である。陵寺木簡の成立時期である6世紀は、中国南朝の五経博士が百済にもたされ、中国に留学していた僧侶が帰国した時期でもある。漢文の受容と活用において、仏教と僧侶、経典などが重要な媒介体であったことを示唆する。
|
![]() © 2007-2011 The University of Tokyo
© 2007-2011 The University of Tokyo